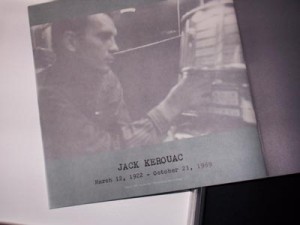 《12月16日からつづく》
《12月16日からつづく》
サド・ジョーンズは1956年録音の3枚のアルバムをブルーノートからリリースしている。当時のサドはカウント・ベイシー楽団の作曲、編曲をしていたが、3枚のアルバムはスモール・コンボによるハード・バップだ。とても洗練された美しい都会のジャズをプレイしている。しかし、ぼくはサドのハード・バップが不満だ。スモール・コンボにおいても、アレンジなど曲の構成に費やす比重が、情感を上回っているので、ビッグ・バンド的なハード・バップに聞こえてしまう。
さて、このブログの12月16日で辰巳哲也クインテットの演奏が足かせをはめられているようだ、と書いたが、これはサド・ジョーンズのアルバムを聞いていて感じる物足りなさと同じだと思う。50年代、ビバップにアレンジを重視するスタンスが時代の流れをハード・バップへと進ませた。そこから、今に至るまで愛される都会的な美しい、モダン・ジャズの名演奏が数多く生まれた。
曲の構成なくしてハード・バップはないが、同時にビバップのエモーションを捨てたわけではない。第二次世界大戦の終戦をひとつのきっかけに、黒人のエモーションが増幅する。ぼくは当時のグレン・ミラー楽団なんかも好きだが、それをジャズとしてビバップやハード・バップとは同列に置かない。隔てる壁は黒人のエモーションだ。だから、ハード・バップの構成を組み立てただけでは、ハード・バップにならない。50年代から遠く離れた現在に、ハード・バップを甦らせることは、理屈からいって無理なのだと思う。
であるならば、聞くことだって無理というものだ。ところが、世の中には理屈では説明できないことが、ときには起こる。今年の7月14日の『Hard Swing Bop』だ。それは、ハード・バップをコンセプトに回す、阿木譲氏の最初のDJだった。4時間をノンストップで、アップテンポなハード・バップのサウンドの洪水だった。そこにノスタルジーではない、ハード・バップが確かにあった。体力を消耗する一期一会のライブ・パフォーマンスだった。
その後、『Hard Swing Bop』は月に一度の定例パフォーマンスとなり、ウエスト・コースト・ジャズにも及ぶにいたった。そこでは、ぼくが黒人のエモーションと言っていたものが、白人ミュージシャンにもあることを認識させられた。
さて。今月15日の5回目の『Hard Swing Bop Special 』の深夜、客の大半は立ち去り、カルテットも東京へ車をスタートさせた。ここで、阿木譲氏はすごいDJを続けた。徹底してスローなバラードを回す。ブリッジにビート詩人ジャック・ケルアックのポエトリー・リーディングを使いながら、コルトレーンなどのバラードが流れる空気感ははんぱじゃなくって、ぼくは立ち去ることができなかった。ハード・バップは時代のエモーションだったんだ・・・。その深夜のDJは、ぼくのなかでは、7月の最初の『Hard Swing Bop』とぴったりとつながった。
気がつくと、ターンテーブルの前にDJの姿はなかった。テナー・サックス1本をバックにしたケルアックのポエトリー・リーディングが、早朝の nu things に流れて続けていた。